二八の月

雑僧の雑感 仏暦2568年2月 前半 vol.151
「二八の月」
二八は「にっぱち」と読み、商売において売り上げが低下する月と言われている。これを二八現象と呼ぶ事もあるそうだ。二八蕎麦は、寛政から天保の頃一杯十六文で食べられた蕎麦を、語呂合わせで二八と言った。こちらは「にはち」である。又、蕎麦粉と小麦粉の割合を表す場合にも用いられる。
四六時中といえば二十四時間を指すが、江戸の頃は二六時中。これは一刻が二時間であった為である。落語の『鷺取り』や『湯屋番』等で言われるが、居候は二階に厄介(八階)になるので十界の身の上。これは十階、十戒とも言われるが、正しくは十界であろう。十界は仏教の言葉で地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天・声聞・縁覚・菩薩・仏の事である。かけざんの歴史は古く、紀元前七世紀頃の中国春秋時代にまで遡る。三五夜は十五夜の事で、質屋はぐに(五二)屋。
ビジネス用語の二八は、景気の悪い時期を指す言葉で、二月と八月の事。これにはいろいろと理由があるらしいが、上期と下期の決算月の前月である為、経済活動が停滞するらしい。また、セールの谷間にあたる為に消費を控える傾向にある為とも言われる。八月はお盆休みがあるので、経済活動も活発になるイメージがある。しかし、二月はどうだろうか。お正月の反動で消費を控える傾向にあるのかも知れない。確かに寺の世界でも二月は比較的穏やかである。藪入りは1月15日(小正月)、7月15日(お盆)が重要な祭日であった為、その翌日は休日となった。地獄の釜の蓋が開く日とも言われる。これは地獄の釜が空になる。つまり地獄の責め苦も休みとされる日である。
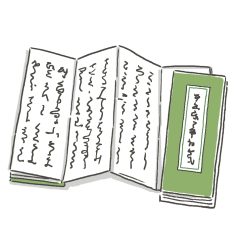
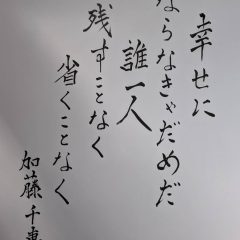



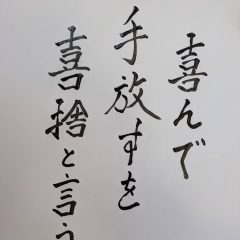

この記事へのコメントはありません。