崇徳院

雑僧の雑感 仏暦2568年4月 前半 vol.155
「崇徳院」
法然上人は、長承2(1133)年4月7日、美作国久米南条稲岡庄、現在の岡山県にご誕生。父漆間時国公、母秦氏。武士が台頭しはじめ、戦乱や飢饉、天災地変が多く起こった地代で、崇徳院の御宇である。
崇徳院といえば
瀬を早み 岩にせかるる滝川の
われても末に 逢はむとぞ思ふ
この有名な和歌を思い出す
百人一首の77番で、たとえ離ればなれになったとしても、再び出逢いたいとの誓いを美しい情景に譬えて詠まれた。菅原道真・平将門と並び、日本三大怨霊とも称される。離ればなれとなったとしても、再開したいとの誓い。これが何時の頃か、失せ物探しのまじないとなった。上の句を紙に書いて貼ったそうだ。落語『崇徳院』はこの和歌が題材となっている。
法然上人のお念仏のみ教えは、極楽浄土に生まれたいと願い南無阿弥陀仏と称えたならば、臨終に阿弥陀様のお迎えを頂き、極楽浄土に往生させて頂ける。倶会一処と言われるが、この世で離ればなれとなったとしても、南無阿弥陀仏と称える者同士、後の世は極楽浄土の一つ同じ蓮の花の上で再会が叶うのである。法然上人は、極楽浄土での再会を
露の身は ここかしこにて 消えぬとも
心はおなじ 蓮のうてなぞ
と詠まれた。保元の乱により、後白河天皇に敗れ讃岐配流となった崇徳院。讃岐では深く仏教に帰依し、極楽往生を願ったとも伝わる。讃岐配流の折に写した経典を朝廷に差し出したところ、呪詛の疑いありと拒否され送り返されたという。時代に翻弄され、怨霊ともいわれる崇徳院ではあるが、美しく純粋なお方であったのではなかろかとも思う。
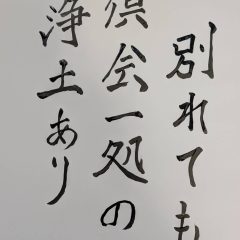
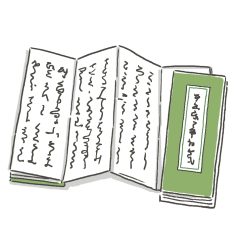



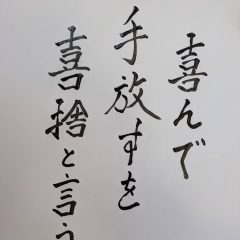

この記事へのコメントはありません。