米将軍

雑僧の雑感 仏暦2568年6月 前半 vol.159
「米将軍」
米の価格上昇に歯止めがかからない。一時期はスーパーの棚から米が姿を消した事もあった。手に入らないのならば、米は日常生活には欠かせない。かつて米離れと言われた時もあったし米不足の時もあった。
徳川幕府は史上稀に見る長期政権であった。その基盤を支える政策は数あれど、貨幣の統一が大きいのではないかと思われる。天下統一を成し遂げた徳川家康は、慶長6年に大判、小判、一分銀、丁銀、豆板銀の五種を発行する。それまでばらばらであった貨幣が、大きさ、重さ、金銀の含有量が統一されたのである。三代将軍家光は銅銭である「寛永通宝」を発行し、金・銀・銅の三貨制が確立する。三貨制は、三種の貨幣が流通する事で、これを変える事が両替である。
貨幣の統一は果たしたものの、幕府や諸藩の収入源は米であった。米は気候の変動や災害等で価格が変動する。米の価格が変動すれば、資産価値も当然変動する。八代将軍徳川吉宗は、財政難に陥っていた幕府を立て直すために米価格の対策に着手し、米価の引き上げをはかると同時に、新田開発を奨励して「米将軍」と呼ばれた。「享保の改革」を推し進め、幕府中興とも言われる。米価の引き上げは、幕府の財政の基盤を確固たるものにしたのだろうが、庶民の生活に影響はなかったのだろうかとも考える。米価の高騰の原因は、昨今の猛暑の影響とか、作付面積の減少とか、インバウンド需要の増加とか、いろいろらしい。備蓄米の放出が話題となっている。米価が安くなる事は悪い事ではない。しかし、価格破壊が起きる可能性も考えられる。今回の放出が生産者、販売者、消費者の三方良しとなる事を願うばかりである。
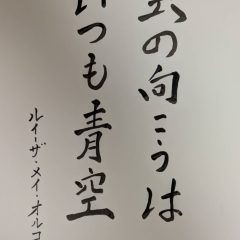




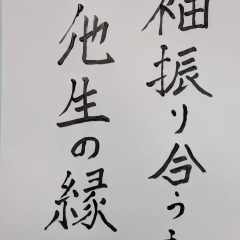
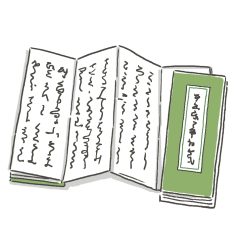
この記事へのコメントはありません。